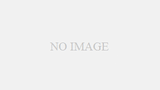動画解説
見どころ:その1
最近、アンチエイジングのサプリが多いが何がいいか?コエンザイムQ10とかNMNとか?最近ネットでよくみる「デアザフラビン」について早速調べてみよう。
見どころ:その2
ネット情報だとデアザフラビンはNMNと比べてミトコンドリア活性が数十倍とある。ノーベル賞を与える世界的権威のカロリンスカ研究所で研究開発とある。夢のアンチエイジング素材かも。デアザフラビンTND1128という名前もかっこいい。詳しく調べるには論文を読まないといけない。今のところデアザフラビンTND1128でちゃんとした論文になってるのが3報。そのうち1つが脳の神経細胞にデアザフラビンを振りかけて、神経細胞が成長したという論文。残りの2つの論文はマウスにデアザフラビンを注射して脳のカルシウム濃度、ATP産生が増強したという内容。サプリメントなのにマウスに注射では参考にならない。NMNのサプリメントと比較しているが、宣伝のように30倍40倍とはかなり盛っている。カロリンスカ研究所のデータもない。すると、あの宣伝の謳い文句はどこから出てきたのだろうか?
見どころ:その3
色々と調べてるとデアザフラビンTND1128について分かった。デアザフラビンというのは1980年頃、メタン産生菌という微生物の中から見つかった。色々調べるとビタミンBに型が似ているということが分かった。しかし、デアザフラビンTND1128は最近合成された全く新しい化合物である。それは口に入れてもいいものなのか?ネットにはビタミンBに似ているから大丈夫とのこと。しかし、化学合成品はちょっとでも形が違うと毒になったりもする。副作用の被害が出たサリドマイド事件もアミノ酸から作ったから安全と宣伝していた。しかし、色々な安全性実験をしていると説明がある。新しく化学合成されたまだ人が口にしたことのないものは、医薬品と同じくらいの安全性のデータが求めれるが、これは普通の食品なみの安全性試験。では毎日デアザフラビンを飲み続けたらどうなるか分からないということ?あるお医者さんの報告では1000人に2人の肝臓障害があったとのこと。1000人に2人というのは多いのか少ないのか?食品に例えたら高い確率なのではないか?製品が1000個売れたら2人が肝臓障害になるという計算。化学合成品というのはそんなに危険なのか?化学合成品が危険なわけではない。ビタミンCも化学合成品がある。だが、人がまだ口にしたことがない化学合成品となると慎重になる必要がある。
見どころ:その4
NMN、コエンザイムQ10、5-ALAはどうなのか?それらは元々人体にあり、自然界にも広く存在し、色々な検査もしていrのでサプリメントとして大丈夫かと。デアザフラビンは人体に存在していない上、自然界にもほとんどないのでそれを合成してサプリメントにすrのは怖くないか?一番いいのは厚生労働省に食品として認めてもらうこと。しかし、厚生労働省はデアザフラビンをまだ食品として認めていないとのこと。では、かなりグレーな感じで販売されているということ?まだまだ安全性は分からないのでそう言われても仕方ない。
見どころ:その5
デアザフラビンをネットで見ているとアンチエイジングに良さそうだ。その効果だが、エビデンスには色々なランクがある。デアザフラビンは細胞実験、動物実験、論文が3本、あとは医者が観察した結果なのでエビデンスレベルは一番低い方。ではどうしてNMNより40倍世界最強のミトコンドリア活性剤と宣伝しているのか?販売者がかなり盛っている感じがあり、色々と法律に引っかかりそう。薬機法、景品表示法、健康増進法などを守って販売しなければならない。では、世界最強のミトコンドリア活性剤というのはどうなのか?ミトコンドリア活性といっても、結局マウスに駐車した実験結果しかない。「世界最強」とか「◯◯よりも◯◯倍」という表現は「最上級表現、比較表現」といって、その根拠を明確に示さないと景品表示法に引っかかる。「ミトコンドリア活性」も細胞活性という言葉が薬機法違反の事例があるので、NGの可能性が高い。身体の何かを活性化させるという表現は薬機法違反となる。ではNMNと違ってデアザフラビンはダイレクトに上げるというのは?そういう根拠は論文には見つからない。サーチュイン活性も論文にはない。特許をとって素晴らしいというのはどうだろうか?特許は作文の要素があるので科学的根拠にはならない。
見どころ:その6
つまり、消費者リテラシーが大事。医師の書籍もあるが、バイブル商法に利用されるかもしれない。やはりアンチエイジングは、美味しいものを食べてよく寝ること。ビタミンB2もミトコンドリアにいいと論文で紹介されている。
動画の感想
客観的な感想。
全体的にデアザフラビンを闇としての視点で語られているので、かなり偏りが感じられる。例えば、論文に出ているというくだりで、論文がひとつもないと言うなら否定する根拠となりうるが、3つしかないの3つが「しかない」というワードで、マイナスを印象づけているように見受けられた。論文の中身の部分で、マウスへの実験の効果に対して、マウスに打っても意味がないという成分の効能を否定しないで、やり方を否定しているところもわざわざ否定している箇所も少々難癖をつけているように見受けられた、確かに人体への実験が必要なわけだが、どれも最初はマウスなのでは?
次に「あるお医者さんの報告では1000人に2人の肝臓障害があったとのこと。」のくだり。あるお医者さんて誰なのか?肝臓障害って一体何?〜大学や〜病院や医者の名前など何ひとつ根拠がないところが本当にそんなデータあるの?と思ってしまう。しかも1000人に2人というデータをとったということは、その何倍ものデータから分かりやすいキリのいい数字にしたのだろうけど、だったら100人に1人でいいのでは?ツッコミどころが多い部分だ。
そして、厚生労働省が食品として認めていないという部分。いまいち意味が分からないのと、類似の成分で通常はどうなの?という例がないので、印象操作のようにも見えてしまう。
あとは、景品表示法の部分だが、これは成分ではなくて販売者の部分であり、ちょっと違う話なのでは?コシヒカリが世界最強のお米と表現して、それはコシヒカリの問題ではなく販売者の問題でありコシヒカリが怪しいと繋げるのは、また別の話なのでは?と思った。
【YOUTUBE動画解説】合成品デアザフラビンついに闇が暴かれる?!の動画解説
【YOUTUBE動画解説】合成品デアザフラビン NMNにマウントをとる必要ある?!の動画解説
こちらのサイトでは、正しい5-デアザフラビンのサプリメントの選び方について方法をご紹介します。